国軍法改定のインパクト
先月20日、国軍法改定案が国会で可決された。瞬時に「軍の権限が拡大する」「軍国主義が復活する」「民主主義が後退する」といった懸念が広まり、全国50以上の地域で抗議デモが相次いだ。これまでデモなど起きたことのない地方でも、学生と人権団体が中心となって、抗議運動を繰り広げている。
今後、改定案は大統領の署名を得て法制化される。署名のタイムリミットは4月20日。このタイミングで、再度「新国軍法」への大規模抗議デモが予想される。
4月20日は、プラボウォ政権発足半年に当たる。またメーデーも近い。市民社会の様々な不満と要求が共鳴して、デモ勢力が大きくなる可能性がある。政権にとっての正念場だ。
国軍法改定に対する反対運動は、この国の民主主義を護ろうという市民意識の高さを象徴している。98年の民主化から27年を迎えようとしているが、世代を超えて、デモ参加の正義が引き継がれている。
ただ、今回の国軍法改定が「軍の権限を強めて民主主義を脅かす」というアピールに関しては、センチメントは理解できるが、客観的には飛躍していると指摘せざるを得ない。
新たに現役将校が兼任可となる省庁は、検察庁、国家災害対策庁、国境管理庁、国家テロ対策庁、そして海上保安機構だ。これらの組織には、すでに現役将校が出向してきた。法律を実態に合わせたに過ぎない。法的根拠を得たことで、これらの組織が軍人に支配され軍事化するのか。そんなことは起こり得ない。
では何が問題か。国会審議の閉鎖性である。憲法は立法過程における市民参加を保障しているが、国会は頑なに市民参加を妨げてきた。法改定の草案も公開されず、一部の審議はホテルで隠れて行われ、スピード可決した後も、改定文書へのアクセスを拒んできた。この透明性の欠如こそが問題で、民主主義の軽視が懸念される所以でもある。軍国主義とか軍の政治的復権といった幻想ではなく、国会の態度が問題の本質であろう。
もちろん、国軍法の改定自体にも問題は別にある。プラボウォは、軍人の定年年齢を現在の58歳から60歳に引き上げ、さら特別な場合は65歳まで現役延長が可能な制度を導入したく、法改定を指示した。大統領に仕える国軍司令官や陸軍参謀長が、ほぼ毎年定年で交代する現在の状況から、4〜5年は一緒に仕事をする安定的な関係に変えるためには、将校の定年延長が必須だと考えている。
その法改定で、組織に何が起きるか。将校団の肥大化と世代交代の鈍化が予想される。今でも将官の数は過剰で、任務のない「職なし将官」が181名に達している。大佐でも238人が職なし状態だ。現役年齢の引き上げが決まれば、将校のポスト不足は更に深刻になり、軍の士気低下が大いに懸念される。
その問題解決として、軍幹部は早期退役の制度化を図っている。今回の国軍法改正に盛り込まれたのが、他の行政機関に「退役して異動」するキャリアパスだ。これが軌道に乗れば、肥大化する将校団のスリム化に貢献すると彼らは期待する。
このように、国軍法の改定をめぐり、軍幹部の思惑と市民社会の危機感の間に大きなギャップがある。この溝を埋めないと、相互不信は高まる一方だ。対立もより先鋭化しかねない。プラボウォの対応が注目される。(本名純・立命館大学国際関係学部教授)
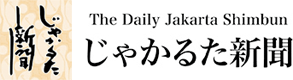




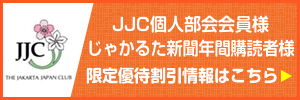

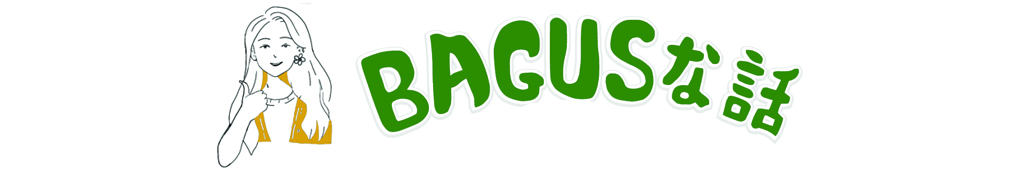





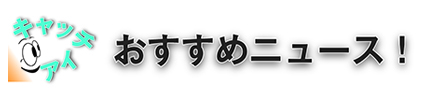


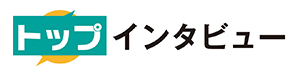

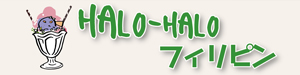


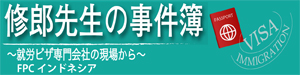





 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について