歳出削減
プラボウォ政権で予算捻出のための大幅歳出カットの議論が佳境を迎えている。無料給食制度をはじめ、食糧・エネルギー自給、国防予算増強などへの予算配分のため、総額307兆ルピア(約2・9兆円相当)の歳出削減が目標とされているが、これは国家予算の8・5%に相当する規模で、行政運営はもとより経済全体への影響も無視できない規模だ。
各省庁とも出張や研修の一時凍結などの対応をスタートさせているようだが、トップダウンで示達されている削減案は、特定の省庁に削減額が集中している。最も大きな削減幅を課されているのは公共事業省だが、昨年度実績の約7割減(81兆ルピア相当の削減)と、かなりドラスティックな規模となる。公共インフラを担う同省は、高速道路や水資源関連の開発を中心に民間投資を募ることで削減分を補っていく目算だが、これまでの官民連携の実績に照らすと圧倒的に不足が出る可能性が指摘される。教育関連の省庁予算もこれに次ぐ削減幅(31兆ルピア)で、特に高等教育の削減幅が大きい。教員等の人件費が予算の太宗を占める中で、教育の質の低下も懸念される。
国防省や国家警察などは当初は削減対象外とされていたが、急遽先週になって予算削減は例外なく全省庁・政府機関が対象となることが示達された。削減額の多寡はともかく、みんなで痛み分けという方向に舵が切られたようだ。
いずれにせよ既に経費節減の動きは至るところで始まっており、非正規スタッフの解雇など雇用への影響も出始めているようだ。無料給食制度のGDP貢献はプラス0・1%程度と言われているが、雇用吸収力の高い建設関連の公共事業にネガティブな影響がでるとなると、ネットでの経済効果はマイナスに働く可能性もあるかもしれない。
予算配分のプロセスは、国に限らず、企業を含めどんな組織にも共通して存在する。ただ、どんなやり方が望ましいかについて単一の解があるわけではない。無用な混乱を避けるため、予め定めたフォーミュラに従って配分するといったケースもあるだろうが、戦略的意図や環境変化を反映させようとすると、どうしても組織内での調整が必要となる。
アプローチとしては組織トップの意図に基づくトップダウンと、現場が要望を上げるボトムアップの両方があるが、多くの組織はその両方を組み合わせて運用しているのではないだろうか。もっとも予算権限を持つ側と現場側との情報格差が常に存在すること、また予算増減の影響が及ぶ範囲や時間軸はまちまちでその時点での評価が難しいこと、などからなかなか意見が定まらないケースも少なくないだろう。
ただトップダウンとボトムアップとのすり合わせの過程では、相互のレビューやチャレンジのプロセスが出てくるはずで、予算配分プロセス自体の意味は、そういったプロセスを通じて得られる納得感をしっかり作り出せるかどうかにあるのではないだろうか。その納得感は組織パフォーマンスにも影響するであろう。
トップダウンのアプローチが強い場合、それが持続的な実行力を伴う強いリーダーシップによるものなのか、それとも単に強権的な手法をとっているだけなのか、これは外からはなかなか見分けがつかないことが多い。今回の大規模な予算配分シフトがどのような結果をもたらすかを見極めるには、ある程度の時間の経過が必要だろう。ただその成否は、予算配分の結果のみならずプロセスにも依存しているのではないだろうかと感じている。(三菱UFJ銀行ジャカルタ支店長 中島和重)
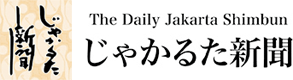




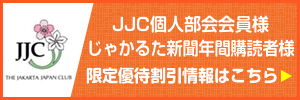


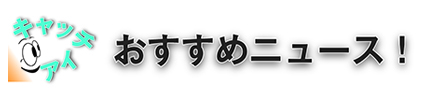

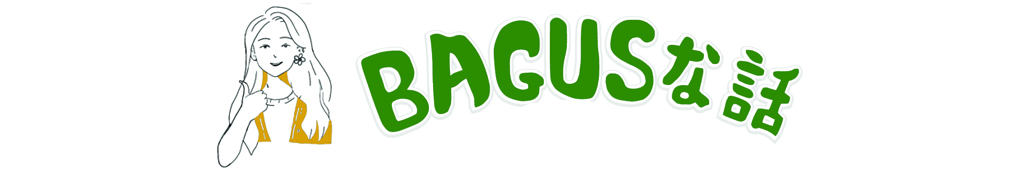




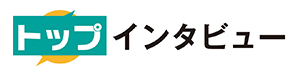

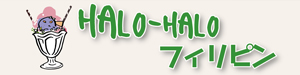



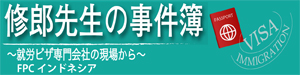





 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について