輸出の伸びしろ
プラボウォ政権が発足して3カ月余り、活発な外交活動や無料給食制度の素早い実施など、予想以上に早く独自色を出してきているとの印象を持つ人も少なくないだろう。新政権が掲げる公約の中でも、5年間の任期中の8%成長達成は、位置付けの高い目標として受け止められている。直近では経済関連の各省庁を中心に、8%成長実現のためにそれぞれがどんな貢献をしていくのかについての議論が活発化している模様だ。
先日、商業省からもブディ・サントソ大臣自ら8%成長の実現をサポートする輸出額の増加率目標が示された。2026年から29年にかけて各年毎に7・1%、7・9%、8・8%、9・6%と駆け上がっていく意欲的な目標だ。インドネシアのGDP成長率に占める輸出の貢献度は常に高いというわけではないが、より大きな寄与度を占める民間消費や設備投資は大きく伸びることも減ることもなく安定しているので、数年単位で成長率を引き上げようとすると輸出増加に牽引役としての期待がかかるのも頷ける。
インドネシアの輸出は石炭やパーム油など天然資源由来の品目が約半分を占めるが(他の主要アセアン諸国で輸出の50%以上を占める工業製品はインドネシアでは15%程度)、過去の輸出高の推移を見ると資源価格のトレンドと強い相関を示していたことがわかる。2000年代前半には輸出増加率がコンスタントに二桁成長を実現していた時期もあったが、それ以降に輸出額が8%以上の成長を記録したのは、10〜11年や21〜22年など資源価格が大きく上昇したタイミングに限られる。近年、資源価格のトレンドは地政学要因に左右される度合いが高く、先行きの予測はあくまでも不透明だが、足下では低調な中国経済や米国での石油・ガス掘削回帰など需給緩和要因が強く、もちろん品目による差はあるものの、全体で見ると現状の低水準が継続するというのがメインシナリオとなろう。
資源下流化政策はプラボウォ政権下でも引き続き注力分野と位置付けられ、高付加価値化による輸出政策の一丁目一番地となる。ただ下流化の拡大が進むにつれてここへきて新たな課題も出始めている。
昨年末、エネルギー・鉱物資源省はニッケル価格の低迷を受け、同鉱石の採掘枠の大幅削減案を打ち出した。これに対し、下流化推進にブレーキがかかる、精錬工程での稼働にも悪影響が及ぶとの懸念が出始めている。
ニッケルについては増産で世界シェアを高めつつ禁輸と下流化でバーゲニングパワーを握るというのが基本戦略であったが、その地位にたどり着く前に自らの供給増によって価格低下を招くというジレンマに直面していると言えよう。
下流化政策の対象範囲拡大についても、精錬工程への投資リターンの水準に関わらず一律に下流化が進められることで、アウトプットとしては付加価値の低い工程に多額の設備投資がつぎ込まれる懸念がある。
8%成長目標はこれまでの経済・産業政策を成長促進的な視点で見直す、という観点では非常に意味があると考えられる。ただ政策介入が強くなり市場メカニズムを歪める度合いが大きくなると、様々な部分で副作用を産むリスクもあるのではないだろうか。(三菱UFJ銀行ジャカルタ支店長 中島和重)
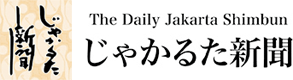




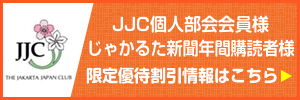


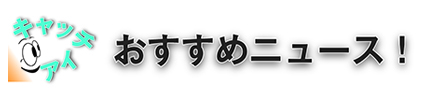

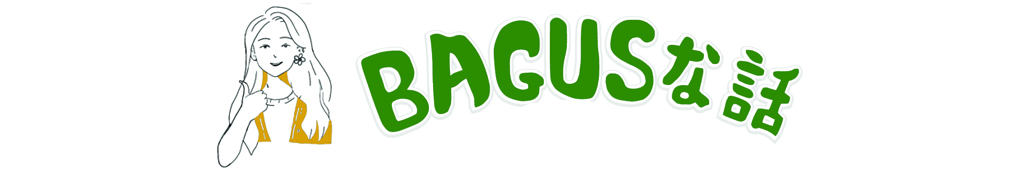




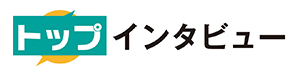

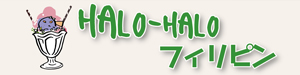



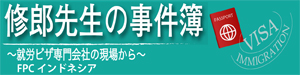





 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について