【育まれた交流 次世代へ 気仙沼とインドネシア】(上) 残ったつながり大切に 力合わせパレード復活
今年8月、東日本大震災による中断を経て「インドネシア・パレード」が宮城県気仙沼市に戻ってきた。主要産業のマグロ遠洋漁業の船員の大半をインドネシア人が担う気仙沼で10年間、続いてきた草の根交流は、震災後、真っ先に駆け付けたインドネシア人道支援チームの活動やユドヨノ大統領の慰問、2年振りのパレードへとつながった。パレード復活を目指して集った多彩な人々の言葉から、日本とインドネシアの新たな交流の芽生えをつづる。(関口潤)
「高校生のときに見ていたドキュメンタリー番組で数秒間、バリの踊りが映って。音楽から雰囲気から目の動きまで、一瞬で心を奪われた」。そう懐かしそうに振り返るのは、パレード前日、巨大なオゴオゴの設置作業に精を出していた大澤光志(みつゆき)さん(36)。
大学2年のとき、後に妻となる彼女と初めてバリへ行き、その後もバリへ通って舞踊に触れ続けたが、昨年、思い立ってバリ舞踊教室に通い始めた。
その教室を通じて知った気仙沼でのパレードで、思いもよらなかった人たちに出会った。パレードの手伝いのため集まった国際協力機構(JICA)の元青年海外協力隊員たち。養蚕の技術を持ちシニアボランティアだった父の大澤光男さん(63)とともに、同時期に南スラウェシ州で働いていた元隊員たちだ。
「ぼくは単なるバリ好きだったけど、気仙沼で元協力隊の人たちに会って、実際にインドネシアで何かをやりたいと思うようになった」
ほとんどがインドネシア文化に触れるのが初めてのパレードの参加者に、優しい笑顔で化粧と着付けを施していたのはワヤン・デニ・稲葉さん(44)。
舞踊一家に育ったデニさんが日本人の夫との結婚を機に日本へ移住したのは1990年。横浜でバリ舞踊の教室を開き、教えてきた生徒の総数は300人になる。
「津波の映像を見て涙が止まらなくて、何かをしたいと思っていた。そうしたら大使館から気仙沼のパレードを手伝ってくれって電話が来て。うれしくてたまらなかった」
パレードの倉庫と控え室を兼ねた雑然とした旧青果市場でデニさんが化粧をほどこすと、皆バリの華やかな踊り子のように変身していった。
そのデニさんに「息子みたいよね」と言われ、照れながら伝統衣装姿に変わっていった幅野一輝さん(20)。気仙沼でボランティア活動をする東洋大の学生たちのリーダー格だ。
「国際関係とかかわったことがなくて。外国人も周りに全然いない」と話す幅野さんがインドネシアに触れるのはもちろん初めて。「やまんばのようなお面(ランダ)とかでっかいオンデルオンデルとか、びっくりするようなものばかり。刺激的で、そりゃインドネシアって何なんだって、自然と興味持っちゃいますよね」。一緒に歩いたバンダアチェの副市長が喜んでいたのも印象的だった。
ここに来たのは、気仙沼の町内会の祭りで特大ゴマを回した鈴木敦雄さん(53)の取り組みを手伝ったことがきっかけだった。「鈴木さんはパワフル過ぎて。大人って普通、冷めてるものだと思ってた。だから学生のうちにいろいろとやろうと思ってた。でも鈴木さんの周りはみんな本当に活動的なんです」
10年前、鈴木さんが「バリのパレードをやるんだ」と提案すると、「何で気仙沼でバリなんだ」と猛反対に合った。だが、鈴木さんは磁石のように人々を引きつけ、規模は年々拡大。駐日大使もはるばる駆け付けるようになった。
昨年6月、ユドヨノ大統領が鈴木さんの住む仮設住宅へ慰問に訪れ、今年4月に初めて訪れたジャカルタでは、東北出身者を中心にパレード再開に向けた支援活動が始まった。鈴木さんの持つ磁力はより強まったようだ。
パレードが終わって2カ月。「残ったものは、新しい人とのつながりと今までの人とのつながりの深まりだった。震災はあまりにも大きいマイナスだったけど、パレードの再開を一つのきっかけにつながりができたことはうれしい」。「来年以降のパレードも、ほかの分野の協力にも、できたつながりを大切にしながら一歩ずつ前に進んでいきたい」と鈴木さんは力を込めた。(3回連載、つづく)






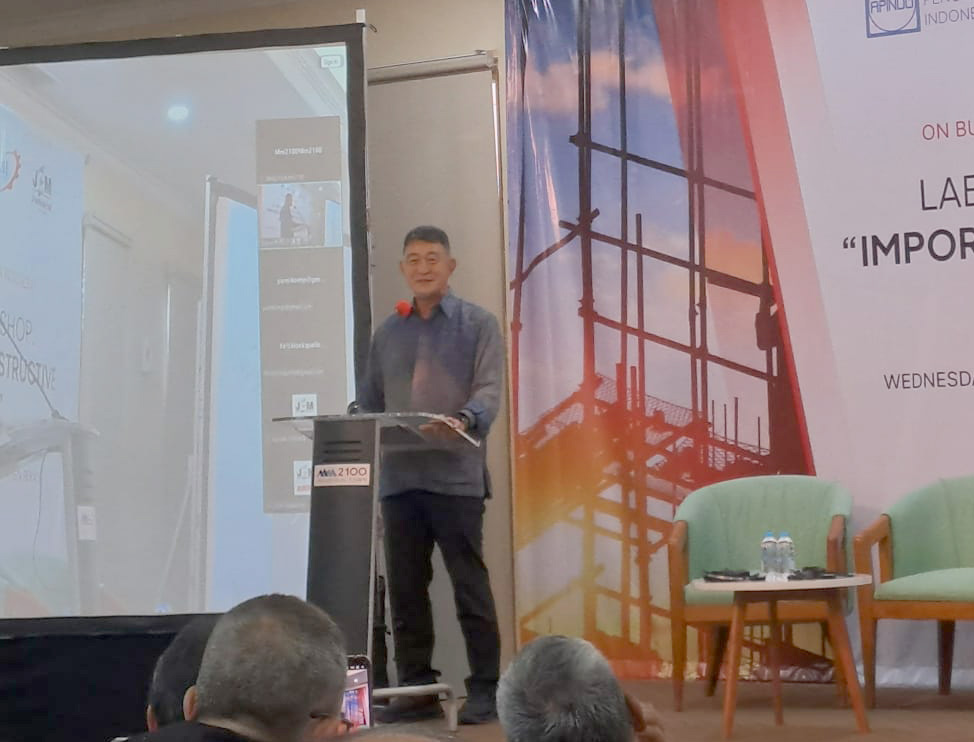

























 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について