収益性に苦しむ再生可能エネルギー
再生可能エネルギー開発が思う様に進んでいない。2023年時点で発電のエネルギーミックスに占める再生可能エネルギーの割合は13・1%に留まり、同年目標である17・9%に対し大幅に遅れている。2014年の国家エネルギー政策(NEP)では、25年までに再生可能性エネルギーの利用割合を23%、30年には26%を目標としていた。しかし、25年の目標達成はもはや難しく、NEP改定案では、25年目標を17~19%に引き下げると見られている。
地形多様性を持つインドネシアは、太陽光、風力、水力、潮力、バイオガス、地熱発電など大きな可能性を秘めている。国家エネルギー評議会の試算では、太陽光が最もポテンシャルが高く3294ギガワット(GW)、次いで風力155GW、水力95GW、潮力63GW、バイオガス57GW、地熱23GWと総量3687GWの発電能力があるとしている。しかし、23年末時点では、わずか14・7GW(0・4%)しか開発を実現できていない。
開発目標と実績の差はコロナによる経済低迷の影響もあるが、電力需要の計算において年率7~8%の経済成長を前提としていることが大きな要因と考えられる。その結果、国営電力会社PLNでは2023年時点で、総発電能力7・2万メガワット(MGW)に対し、ピーク時負荷は5・8万MGWと設備過剰になってしまった。PLNとしては独立系発電事業者(IPP)から再生可能エネルギー電力を買電する意欲が沸かない状況となっている。
IPP事業者の収益性も課題だ。IPP事業者からPLNへの売電価格は固定価格買取制度(FIT制度)にて決定される。ただし、インドネシアのFIT価格は他ASEANと比して低い水準に留まる。例えば、太陽光発電のFIT価格はUSD5・90セント/kWhであり、一人当たりGDPが同水準のフィリピン・ベトナムよりも低い(各USD7・60セント/kWh、USD7・09セント/kWh)。20年インドネシアにてグリーン電力証書(REC)が導入された。当初、IPP事業者はRECによる収益アップを期待していたが、PLNのみが販売可能であり、その収益はIPPに直接落ちないスキームであった。
発電コストの高さも収益を圧迫する。エネルギー研究機関のIESRによると、インドネシアにおける平準化電気料金(LCOE)は石炭火力でUSD5・68~8・71セント/kWhである一方、太陽光はUSD5・79~9・76セント/kWh、風力8・36~11・31セント/kWhとコスト高となっている。
それらの課題に対し、インドネシア政府は再生可能エネルギーの普及に向けた各種インセンティブを提供。タックスホリデー(5~20年間の法人税免税など)、タックスアロケーション(投資総額の最大30%を6年間課税所得より減額など)、VAT免税(特定機器の輸入VAT減免など)、輸入関税免除(現地非製造機器の輸入関税免除)など、様々な税制優遇を講じた。
しかし、全体感を改めて整理すると、発電能力過剰に加え、他ASEAN諸国より低いFIT価格、収益貢献のないREC制度、化石燃料より高い発電コストなど、再生エネルギーを推進するには構造的な課題が存在する。承認プロセスに時間を要するという以前の問題として、投資対効果を見込みにくいという根本的な問題に直面している。インドネシアには豊富な再生エネルギーのポテンシャルが存在する。それら自然資源を有効活用するためにも、FIT価格の改定、税制優遇など、再生可能エネルギーを担うIPP事業者の収益性向上に資する更なる一手を期待したい。(三菱UFJリサーチ&コンサルティング・インドネシア現地法人社長 中島 猛)
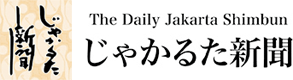




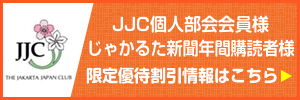


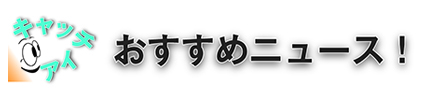

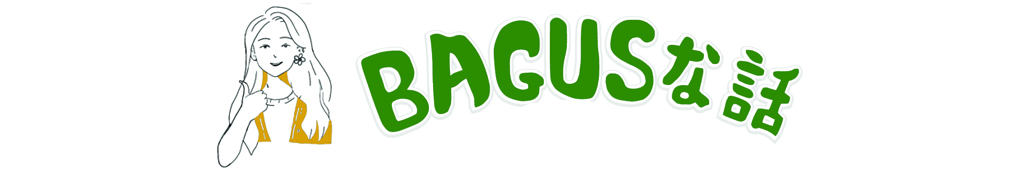




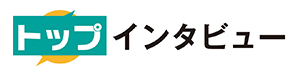

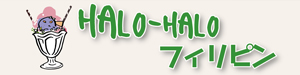



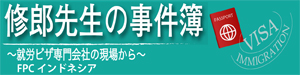





 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について