『EdTechの可能性』
インドネシアの教育産業が揺れている。無料給食制度などへの予算配分のため、各省庁で歳出削減目標が定められた結果、教育関連予算も31兆ルピア(約2900億円)の削減を迫られている。特に高等教育での予算削減は大きく、インドネシア大学では国際ジャーナルの購読停止など隅々まで予算削減を進めている。2022年のPISA(OECD生徒の学習到達度調査)ランキングでは、インドネシアは69位とASEAN主要国の中でベトナムに次ぐ下位2位となっており(日本は総合3位)、教育の質向上が求められていただけに、懸念が広がっている。
そんな中、EdTechの活用可能性が注目を浴びている。EdTechは、オンライン学習などに留まらず、AIを活用することで、個人に合った教育プログラムの提示、質問への自動回答など、より効果的な学習を可能にする。また、学習管理システムにより学習進捗を都度確認でき、授業の資料作成も簡素化させることができる。
East Ventureの報告書によると、EdTech市場は22年時点で1・5兆ルピア(約130億円)。27年には2・9兆ルピア(約250億円)規模となり、年平均14・9%で成長が見込まれる。コロナ禍の在宅受講により急速に市場は拡大。対面授業の再開により、成長率はやや鈍化しているものの、堅調な成長が期待されている。
一方、課題も存在する。ユーザーの利用料支払いに関する懸念だ。家計総支出に対する教育関連支出の割合は都市部でも約4・0%弱、地方では約2・4%に留まる。ユーザー拡大のため無償サービスから開始し、有償サービスへ誘導することになるが、切替がスムーズに進んでいない。13年頃より新規参入が相次ぐものの、利益を確保できている企業は25%程度に留まっており、薄利多売ビジネスに依存しない事業展開が求められる。
サービスの高度化も必須だ。政府が提供するEdTechサービスはSTEAM(科学・技術・工学・芸術・数学)、言語などの知識学習が中心。尼国企業はそれらに加え、学習管理システムや運営・教員支援システムなども提供している。しかしながら、現時点においては対面学習と同様の知識偏重の一方通行型が主になっており、対面学習では補えることの可能な相互補助の関係がEdTechでは希薄になることから、継続性・有効性に陰りが見える。
インターネット環境の更なる整備も期待される。EdTechユーザーの75%が携帯を利用していると言われているが、インターネット接続の問題で学習に支障をきたす事例も散見される。インドネシア政府は27年までに4Gユーザーを74%、30年までに100%とする方針を掲げている。今後、AIやバーチャル(VR)なども活用した質の高いサービスを提供していくためには、乗り越えるべき課題である。
政府予算が削減される中、教育の質低下を食い止め、更なる向上に資するEdTechへの期待は大きい。ユーザーの支払能力、知識偏重に伴う継続性・有効性への懸念、収益化への苦慮などの実態を鑑みると、一計を講じる必要があろう。まず、支払能力・資金力を比較的期待できる私立の高等教育や社会人を対象に、AIやVR活用によりカスタマイズされた質の高い教育を提供する。合わせて学習管理システムや運営・教員支援システムにより運営の効率化を図る。収益を確保しつつ、サービスを充実させた上で、私立の中等・初等教育へ展開し、公立の高等教育から中等・初等教育分野へ波及させていく。最終的な普及までには時間を要するが、優先順位を明確化し、資源を集中させ、着実に歩を進めたい。成長期待の大きい市場だが、長期的な人財不振を防ぐため、更なる加速化を図れないだろうか。(三菱UFJリサーチ&コンサルティング・インドネシア現地法人社長 中島 猛)
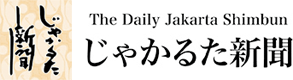




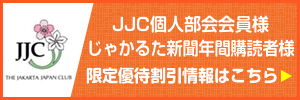


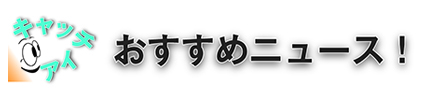

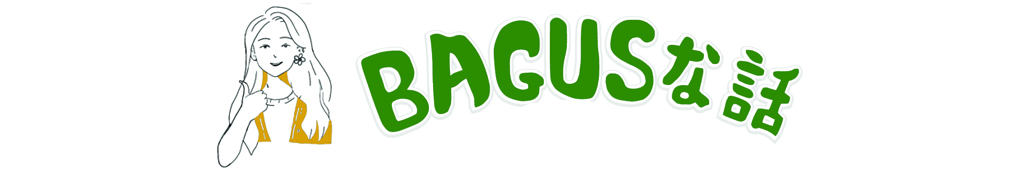




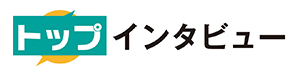

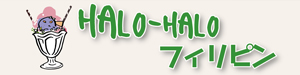



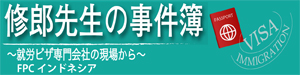





 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について