トランプ政権下のドル金利
トランプの大統領就任から3週間、予想通りにというべきか、ほぼ日替わりで想定外の発言が連日ニュースを賑わせている。ただ米国経済への影響、特に懸案のインフレ再燃リスク、という視点で見ると、少なくとも現時点までのトランプ政権のアプローチはある程度計算されていて、あくまでも安全運転の範囲内というようにも見受けられる。
政権公約のうちインフレにダイレクトに効いてくるのは関税引き上げであろうが、これまで実際に発動されたのは中国からの輸入製品に対する10%の追加関税にとどまる。カナダやメキシコ向けの25%関税適用についてはいったん猶予期間が設けられたが、これはいずれも国境警備強化などに両国が合意したことによる猶予措置で、これらから類推すると関税交渉が主には外交カードとして使われること(逆にすべてカードを切ってしまうと交渉材料にならなくなる)がより鮮明になってきたとも考えられる(併せて、カナダとメキシコ両国が即座に報復関税を示唆したことも適用猶予への大きな要因となったであろう)。
先月29日、米連邦準備理事会(FRB)はドルの政策金利据え置きを決定した。当日のパウエルFRB議長の会見では、トランプ政権の政策影響についての質問が相次いだが、あくまでも実際の政策が実行に移されるまでは様子を見る必要があるとのスタンスを崩さず、トランプ政権の政策が金利据え置きに影響しているとのニュアンスを与えることを巧みに回避していたのが印象に残った。
一方、トランプ氏の方はなかなか利下げを進めないFRBに対して批判的なコメントをしているが、それでも第1次政権時のFRB批判のトーンや頻度に比べると、まだ抑制が効いている。
ただ何よりも足下の米国の経済統計は、金利据え置きをサポートするに十分な内容と言えよう。インフレ率は3ヶ月連続で上昇率が加速、より長期のトレンドを示すコア指数は低下トレンドを維持するが、消費者調査に基づく1年先の予想インフレ率は直近で4・3%と大きく上昇している。雇用も強く、11月と12月の非農業部門の雇用者数は予想を上回る高水準。先週末に出た1月の数字は多少減速したが、それでも平均給与上昇率や失業率の推移を見ると雇用が堅調なのは明らかだ。
FRBは、政策金利の決定に関わる連邦公開市場委員会(FOMC)の参加者19人による将来の政策金利見通しを公表している(ドット・プロットと呼ばれ、3ヶ月に一度更新)。直近昨年12月時点の予想中央値で見ると、2025年中の利下げ回数は2回(0・5%)。昨年6月および9月時点では4回(1・0%)の利下げが予想されていたことを考えると、かなりペースが後退してきていることが見て取れる。
今後数ヶ月、どのようなシナリオが考えられるだろうか。いつでも想定外のことが起きうる前提ではあるが、米国のインフレ率は再燃とまでは行かないまでも低下幅は限られ、ドルの利下げは年内1〜2回、大統領とFRBの間のテンションは高まるかもしれないが雇用や株価が強い限りエスカレートはしない、といったところかもしれない。
インドネシアは中銀が引き続きルピア金利の引き下げをトライするであろうが、今の政策金利5・75%からあと2回の利下げで、現状のドル政策金利との差が1%を割り込むことを考えると、為替レートへのプレッシャーは高まっていく可能性が高い。引き続き薄氷を踏む利下げであることに変わりはないであろう。(三菱UFJ銀行ジャカルタ支店長 中島和重)
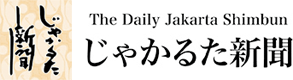




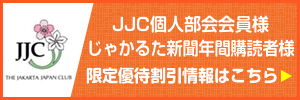


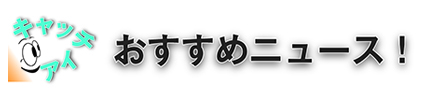

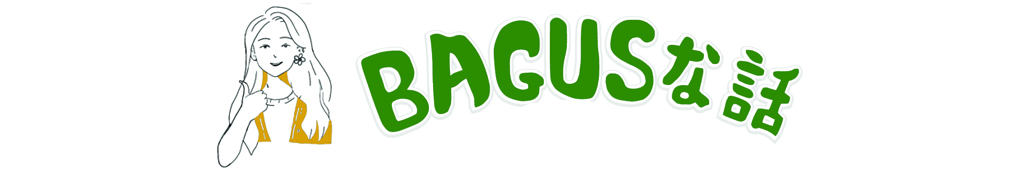




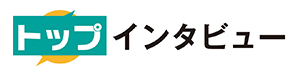

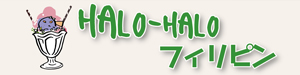



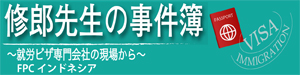





 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について