防災教育、各地に定着 国際交流基金「若者コンペ」 震災経験の日本に関心 応募大半は被災地から
国際交流基金は南ジャカルタのジャカルタ日本文化センターで5日、インドネシア科学院(LIPI)との共催で、インドネシアの大学生や大学院生が地域住民らに防災の考え方を広める取り組みを発表する「日本・インドネシア防災教育 若者コンペティション」を開いた。2004年のスマトラ沖地震・津波の被災地のアチェや06年の中部ジャワ地震などの被災地のジョクジャカルタなど、全国各地から139チーム556人が応募。各地で防災に対する意識が定着していることや同じ自然災害の多発国で、特に阪神大震災以降、防災に関する研究を進めてきた日本への関心の高さをうかがわせた。(関口潤、写真も)
これまでの防災関連の活動と今後の見通し、日本から学びたいことの3点を発表し、専門家らが優秀と評価した6チーム24人が外務省の「キズナ強化プロジェクト」の枠組みで来年2―3月に日本を訪問する。
首都圏で最終審査に残ったのは20チーム中わずか2チーム。ジョクジャやアチェなど、地元の被災地で活動を続けてきた学生団体が大半を占めた。
6チームの一つに入った西ジャワ州バンドンの「コルサ」は、ほかの多くの団体が学校を活動の場に選んだのと異なり、地元コミュニティの中心となっているモスクに着目。コルサのフェリー・アディ・プラセトゥヨさんは、東北の被災地で住民が協働して避難生活を送る映像を見て、日本で「行政と住民の関係について学びたい」と意欲を示した。
特別賞となったアチェの「コンパス」は「歌なら子どもたちにも親しまれる」として、伝統歌に津波が起きたらすぐに逃げることを教える歌詞を付けた歌を地元の小学校などで教えていると紹介した。
国際交流基金ジャカルタ日本文化センターの小川忠所長は、スマトラ沖地震・津波以降、防災が非常に重要かつ身近な問題となっていると指摘し、「熱意は日本の学生以上」と強調。「災害や復興というと医療や技術的な面に目がいきがちだが、心や文化の面でも貢献できる」と述べ、今後も日本の知見を発信していきたいとの意向を示した。
学生らの発表を前に、建築や芸術の技法を防災に生かす活動をしている「プラス・アーツ」の永田宏和さんが講演。05年の阪神大震災10周年事業で、震災の記憶を風化させないために家族や子どもが楽しみながら防災を学ぶイベントを開いたことをきっかけに、活動を広げてきたことを紹介した。
「被災の記憶が薄れても防災への意識が残るよう、日常化することが重要」と永田さん。07年からジョクジャで始めた活動は、すでに現地で自立しているという。「当初は防災のソフト面が弱いということでインドネシアへ来たが、今日はこれだけの学生が集まり、発表のレベルも高く驚いた」と語った。






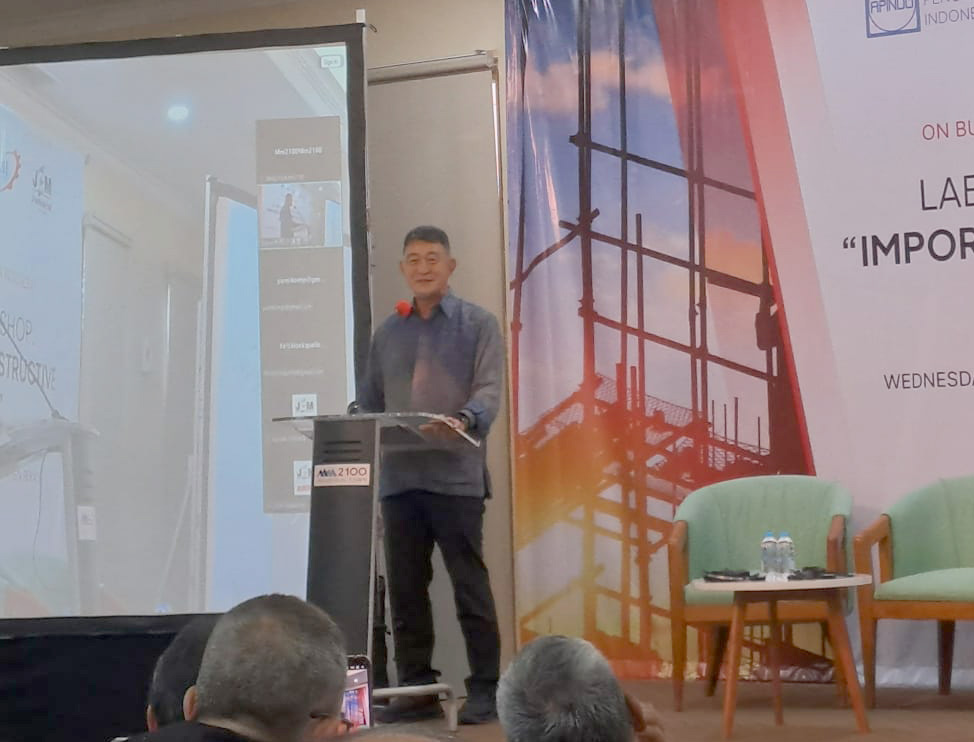

























 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について