【幻のコーヒー復活40年】(4)新しいコーヒー文化を 初の自前カフェから発信
広大なインドネシアの東半分への玄関口として知られるスラウェシ島のマカッサル。中心街のグヌン・ラティモジョン通りの一角に5年前、周囲とは一風変わった店がオープンした。トアルコ・ジャヤ社が経営するカフェ「トアルコ・トラジャ・コーヒー」だ。
店内に入るとアラビカコーヒー独特の芳醇な香りが鼻先をくすぐる。香りも味も重視するハンドドリップ(1杯ずつ手作業で入れるコーヒー抽出方式)によるコーヒーが売り物だ。日本の本格的なコーヒー店では普通の光景だが、開店当時、マカッサルの人々には珍しい店だった。
というのも現地の人々が通う喫茶は「ワルコップ」、いわゆるコーヒー屋台である。そこでのコーヒーの楽しみ方は「トブロック」が主流。コーヒー豆の種類はロブスター。カップにお湯と粉をいれてかき混ぜ、粉が沈殿するのを待って上澄みを飲む。コーヒーの粉粒が舌にザラザラ広がって、慣れない外国人は戸惑う。
そんなコーヒー風土の土地で、全く新しいカフェを開いたのは、「実店舗を通じてインドネシアにまだなじみのないドリップオンコーヒーの文化を広めたい」(トアルコジャヤ社社長兼店長の石井亮さん)という狙いがあったからだ。
背景には、SNSの拡大や外国旅行などを通じ、ミドルクラスを中心に豆の産地やドリップオンの飲み方などにこだわりを持つ愛好家が増える、という同社の読みがある。インドネシア国内のコーヒー消費量は現在世界第5位。中産階級の拡大で2025年ごろには現在4位の日本を抜き去ると予想される。14年ごろ、つまりマカッサルのカフェを開店したころからインドネシアの主要都市では爆発的なカフェブームが起こっている。
実は同社にとってインドネシアでコーヒー店を開くのはこれが初めてだった。企業戦略を込めたアンテナショップである。自社製品を核に、マカッサルの人々に上質なコーヒーをカフェで楽しむライフスタイルを提案し、自社製品の拡販にもつなげる多面作戦である。
マカッサルで続々とオープンするお洒落なカフェやコーヒーにこだわりを持つワルコップ。そのオーナーの一人がファリド・カシムさん(41)。「敷居は低いけど上質なアラビカコーヒーを楽しめるカフェを」と3店を展開する「ワルコップ・ブンドゥ」には「トアルコ・トラジャ」がしっかりメニューの座を占めている。
インドネシア各地の空港の土産物売り場。各種のきらびやかな包装に包まれた「トラジャ・コーヒー」がところ狭しと並んでいる。「トアルコ・トラジャ」にあやかった商品が少なくない。ジャカルタにも、ガヨ・アチェ、フローレスなど、産地名をブランドに売り物にする製品が増えてきた。
ライバル商品ともなりうるコーヒー販売者やカフェの出現は、「幻のトラジャ復活」をかけインドネシアのコーヒー産業育成の一躍を担ってきた同社にとっては痛しかゆしの面もあるかもしれない。確かなことは自社コーヒー農園運営の夢から始まったキーコーヒーの「トラジャ戦略」は40年を経て、同社が想定した範囲を超える広がりを見せつつあることだ。(斉藤麻侑子、写真も、おわり)
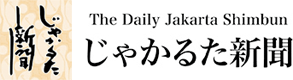





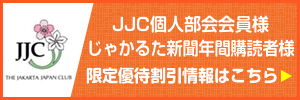


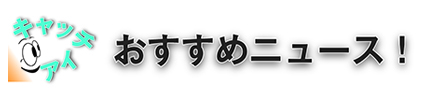





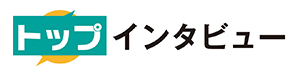

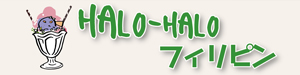



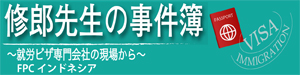





 紙面・電子版購読お申込み
紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について
紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について
電子版への広告掲載について